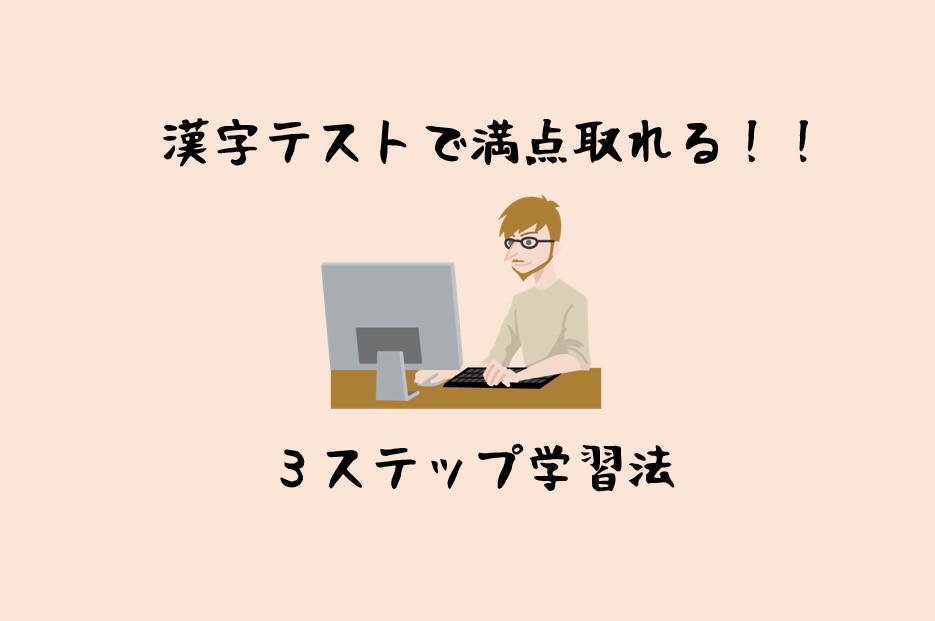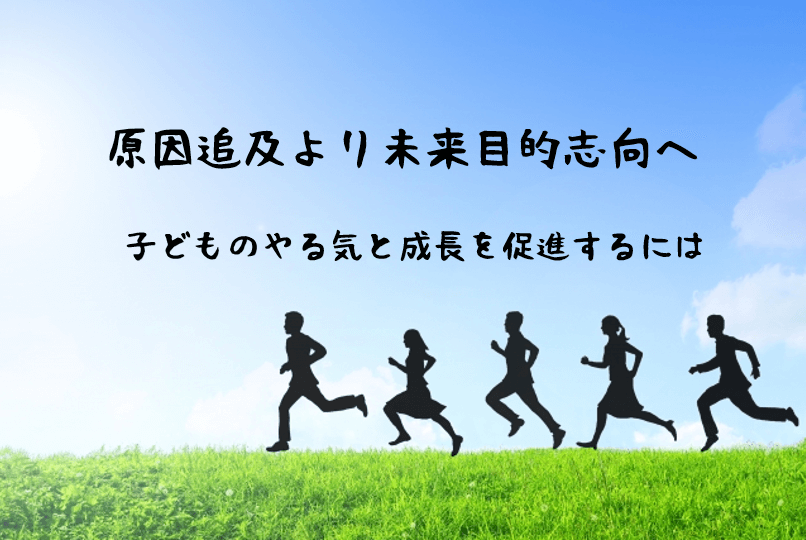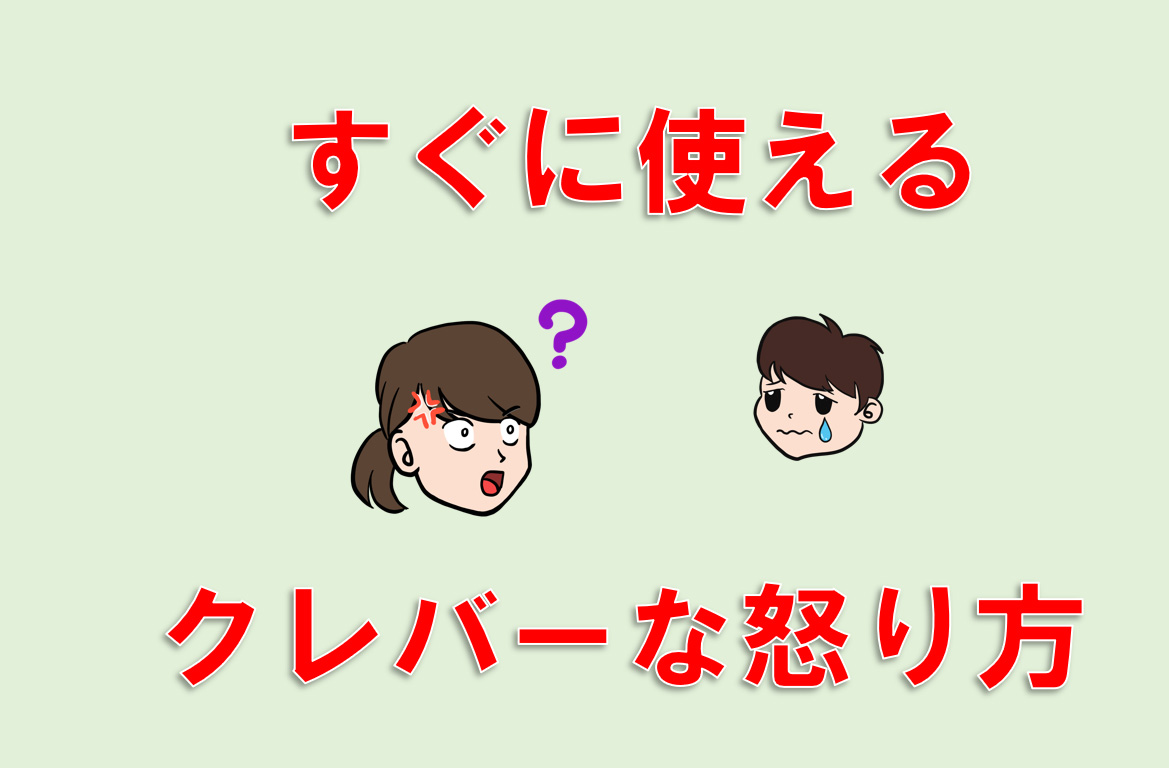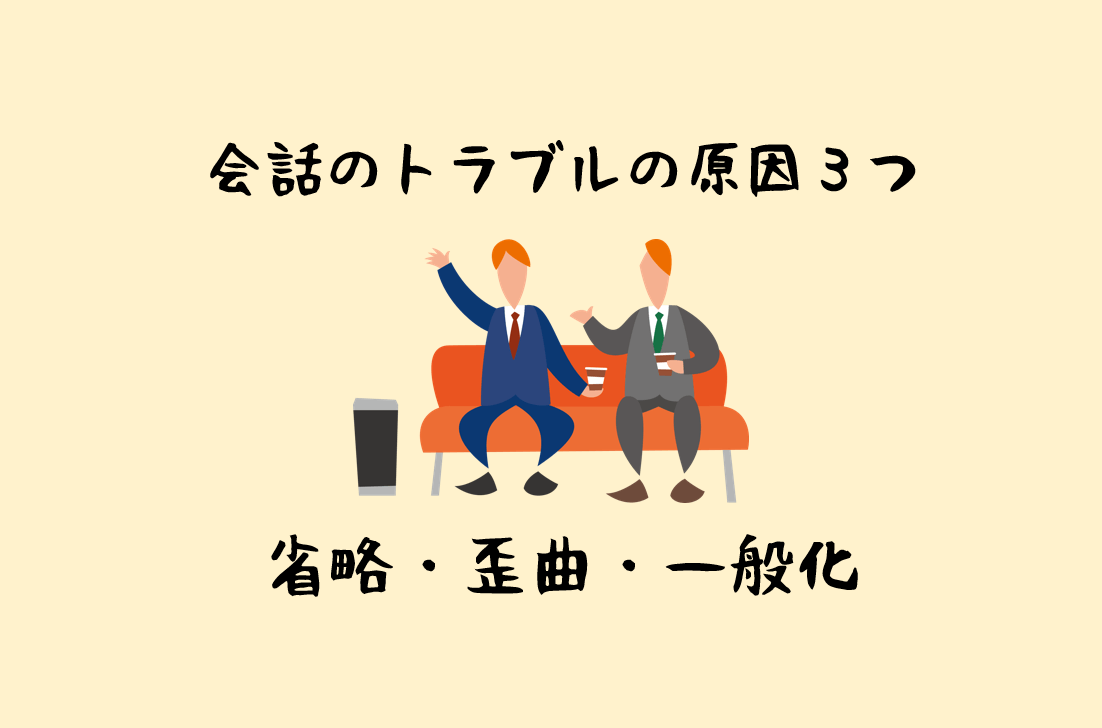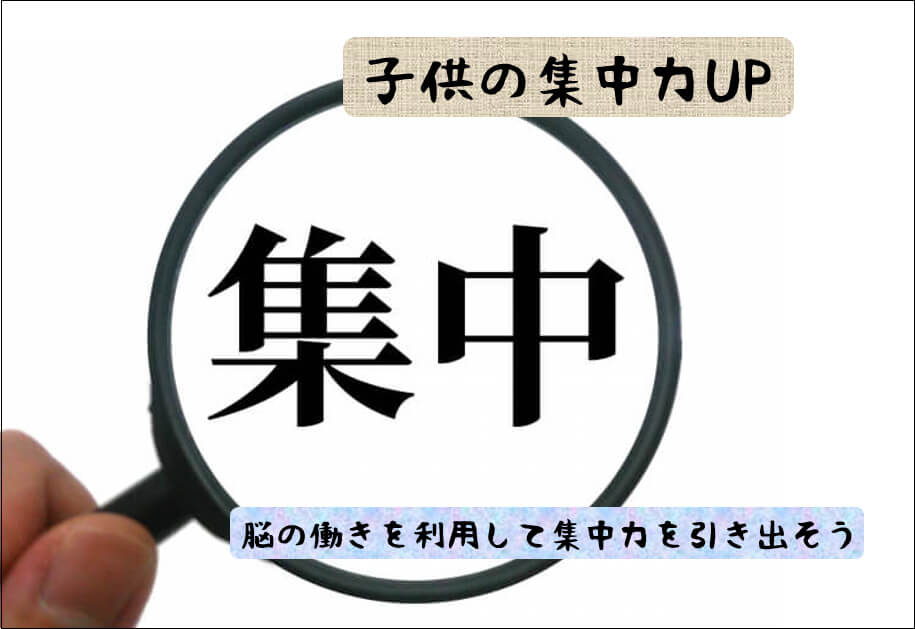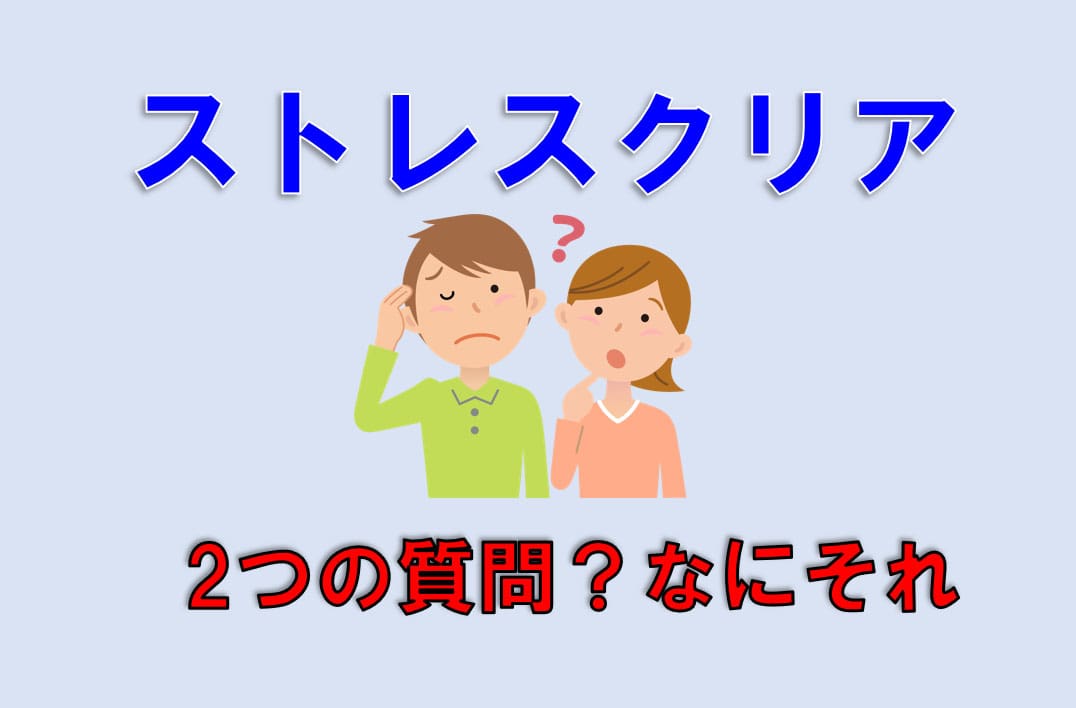学校の授業も全然やる気がなくて、本人は<span lang=”EN-US”>4</span>年生なのに諦めモードです。
新しい学年の漢字をやっても覚えれないんで、この子のレベルに合わせて、<span lang=”EN-US”>2</span>年生くらいの漢字を中心にさせて欲しいと、担任の先生にお願いしました。
この状態じゃ進学できるかも心配です。<span lang=”EN-US” style=”letter-spacing: .6pt;”>
</span>
本人も、やってもできない経験を繰り返して、毎日辛い思いをして過ごしているかもしれないですね。
でも、諦めるのはまだ早いです!
人それぞれ特性があり、得意・不得意、向き・不向きがあって当然です。
学校の一律の学習形態に合わないのであれば、お子さんにあった学習スタイルで力をつければよいのです。
漢字の学習は、コツさえつかめば必ず覚えられるようになるので、新出漢字もぜひやらせてあげてほしいなと思います!!<span lang=”EN-US” style=”letter-spacing: .6pt;”>
</span>
当ブログにお越しくださりありがとうございます。
今回は、<span class=”marker2″><strong>漢字のテストが苦手な子でも、確実に満点がとれる漢字の覚え方について</strong></span>書きました。
この記事を通して、
・記憶は忘れることが前提にあること
・漢字を効果的に、確実に覚えられる方法
について理解できるようになります。
漢字のみならず、他の教科にも流用可能です!
実際の教育現場で実証済みですので、ぜひ最後まで読んで、活用してみてくださいね!
<h2 class=”hh hh16″>記憶のメカニズムを知る</h2>
<img class=”size-full wp-image-2624 aligncenter” src=”https://dylansensei.com/wp-content/uploads/2019/09/6586d84193cc8385917891530a98c056_s.jpg” alt=”” width=”640″ height=”480″ />
【漢字を覚える方法・ステップ1】は、
<strong><span style=”color: #ff0000;”>”</span></strong><span class=”keiko_yellow” style=”color: #ff0000;”><strong><span style=”color: #ff0000;”>記</span>憶のメカニズムを知り、効率的に学習に臨む” です</strong></span>。
記憶の仕組みを知ることで、忘れてしまう自分をむやみに卑下することなく、客観的に自分の能力を見られるようになります。
<h3>記憶は忘れるようにできている</h3>
<img class=”size-medium wp-image-2625 aligncenter” src=”https://dylansensei.com/wp-content/uploads/2019/09/a3bc52919db1b3d943ea8537e92aaca9_s-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ />
記憶には、長期記憶と短期記憶があるというのは、これまでに聞いたことがあるでしょうか。
<strong>長期記憶</strong>とは、<span class=”keiko_yellow”>自分の名前、電話番号、小学校の時の校歌</span>など、いつまでも忘れることのない強い記憶です。
<strong>短期記憶</strong>とは、一時的に記憶はするが、1,2日もすればすっかり忘れてしまうような、ささいなことです。
記憶を長期記憶に保管する役割は、脳の<span style=”font-size: 14pt;”><strong><span style=”color: #ff0000;”>『海馬』</span></strong></span>が担っています。
出来事が短期記憶でなく、長期記憶に保存される基準は、<strong><span style=”color: #ff0000;”>【生命維持に必要か】</span></strong>ということです。
珍しい果物の名前を聞いて一時的に覚えていても、それが生命維持に必要な記憶でないと判断されれば、記憶が薄くなっていき、30日後にはほぼ消去されてしまうそうです。
その果物を食べれば、不老不死を手に入れることができる!となれば、その名前を忘れづらくなることでしょう。
全ての記憶を残していると、人間は混乱を起こし、生きてられないので、生きるために必要のないものと判断された記憶は、積極的に消去されていきます。
<h3>賢い子でも必ず忘れる</h3>
<img class=”size-medium wp-image-2631 aligncenter” src=”https://dylansensei.com/wp-content/uploads/2019/09/7f216e0cfc02299df561bf8a00a459e0_s-300×225.jpg” alt=”” width=”300″ height=”225″ />
上記のことから、勉強したことでも、重要でないと判断したものは忘れていってしまいます。
こないだ習った算数の公式も、うっかり忘れてしまうことだって普通にあります。
それが<span style=”font-size: 14pt;”><strong><span style=”color: #ff0000;”>人間の特性であって、あなただけができないわけじゃない</span></strong></span>、ということをまずは伝えてあげていただきたいのです。
勉強が苦手な子は、これまでに何度も、<span style=”color: #ff0000; font-size: 14pt;”><strong>”自分は頭が悪い”</strong></span> と思わされる経験を積んできています。
それは、単なる結果の一側面でしかないにも関わらず、揺るぎない事実のように自分の中に固定化してしまっています。
すると、<span class=”keiko_yellow”>”今回も覚えられずに悪い点を取ってしまうのは、自分の記憶力が悪いから。”</span>
<span class=”keiko_yellow”>”どうせがんばっても自分には無理”</span> と悪循環の思考に陥ってしまいます。
<img class=”size-medium wp-image-2630 aligncenter” src=”https://dylansensei.com/wp-content/uploads/2019/09/7cd6f3d069c0e2c0d4090c779011b417_s-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ />
ですが、事実は違います。
どんな頭のいい子でも、脳は忘れるようにできているのです。
では、良い点取れる子とそうでない子の何が違うのか。
それは、<strong><span style=”color: #ff0000;”>忘れないうちに、繰り返し見返しているかどうかの違い</span></strong>だけです。
つまり、今、覚えることが苦手であっても、正しい効率的な学習をすれば、すぐにでもできるようになるということです。
<h2 class=”hh hh16″>記憶を上塗りして、濃くする</h2>
<img class=”size-full wp-image-2632 aligncenter” src=”https://dylansensei.com/wp-content/uploads/2019/09/034ce9113b24609efd81813f32484878_s.jpg” alt=”” width=”640″ height=”427″ />
<span style=”font-size: 12pt;”>【漢字を覚える方法・ステップ2】は、<strong><span class=”keiko_yellow” style=”color: #ff0000;”>短期記憶から長期記憶に変換する作業をします。</span></strong></span>
これをすることで、本番のテストでもうっかり忘れてしまうことがないですし、長期に渡って覚えていられるので、学習の積み重ねができるようになります。
先ほどお話ししたように、長期記憶に残るかどうかは、『生命維持に必要か』ということです。
脳の海馬がそう判断すれば、長期的に保存されるようになります。
<h3>あいまいな選考基準</h3>
<img class=”size-medium wp-image-2627 aligncenter” src=”https://dylansensei.com/wp-content/uploads/2019/09/a99fbb10865c0bad4dc92a204b266d1b_s-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ />
長期記憶にするかどうかの選考基準は結構いい加減で、本当に生命維持に関わらないことでも、『頻度』か『強いインパクト』さえあれば、O.Kをもらえるようになっています。
<strong>『頻度』</strong>なら、毎日繰り返し電話番号を復唱していれば、脳は、これは生きていくうえで大事な情報だ!と判断します。
1度きり読んだだけで、本棚の奥に埋もれている本の作者の名前は、必要のないものと判断します。
<strong>『強いインパクト』</strong>なら、高い所から落ちたことや、この場所で1万円拾った出来事、残りのおかずを横取りされたなど、インパクトのある現象が起きた時、生きるために覚えておかないといけないと判断し、長期記憶に保管されます。
<h3>興味のない学習は基本、短期記憶に一時保管</h3>
<img class=”size-medium wp-image-2628 aligncenter” src=”https://dylansensei.com/wp-content/uploads/2019/09/2a7edc7d0ac179a8b8236c75512b44f8_s-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ />
誰でも一度は経験があるかと思いますが、<span class=”keiko_yellow”>こんな勉強が将来何の役に立つんだろう・・・</span>って子どものころ考えませんでしたか?
まさしくそれは、生命維持には必要のないことで、短期記憶に一時的に保存されて、いずれ忘れ去られる記憶なのです。
学校の授業は、勉強が苦手でつまらない子にとっては、短期記憶情報のオンパレードです。
ですから、すぐに忘れてしまって、テスト本番では真っ白ということが起きても不思議ではありません。
では、どうすれば良いか。簡単です。
<span style=”font-size: 14pt;”><strong><span style=”color: #ff0000;”>記憶の上塗り</span></strong></span>をすればよいのです。
興味のない内容ですから、時間が経つにつれて記憶が薄くなっていきます。
少し薄くなった状態の時に、もう一度同じことを覚え直します。
つまりは、<strong><span style=”color: #ff0000; font-size: 14pt;”>復習をする</span></strong>ということです。
<h3>エビングハウスの忘却曲線</h3>
<img class=”size-medium wp-image-2626 aligncenter” src=”https://dylansensei.com/wp-content/uploads/2019/09/a9b90323d2ab3ff9098d83bdf0b84b3b_s-300×169.jpg” alt=”” width=”300″ height=”169″ />
記憶の話で有名なのが、エビングハウスの忘却曲線です。
無意味な言語(ちとへ、なぺぽ、ふへば)などを完全に覚えるまでに10分かかったとして、当然時間が経つと記憶が薄くなって、部分部分を忘れていってしまいます。
20分経つと、薄くなった記憶を元の状態に戻すには、4分かかるそうです。
さらに、1時間後では、5.6分かかり、9時間後には6.5分要するそうです。
1か月後には、約8分を要さないと、はじめに覚えた濃い記憶に戻せないというデータがあります。
つまり、今日覚えたことの復習を1か月以上後にすれば、また一から覚え直す労力が必要ということになります。
なので、<strong><span class=”keiko_yellow”>学習をしてから、時間が経ちすぎないうちに、復習をして記憶を上塗りすることで、長期記憶化されていく</span></strong>ということです。
<h2 class=”hh hh16″>効果的な漢字の覚え方</h2>
<img class=”size-full wp-image-2623 aligncenter” src=”https://dylansensei.com/wp-content/uploads/2019/09/ad3a40e8d7953c3c0057ddb4d9df9e8e_s.jpg” alt=”” width=”640″ height=”427″ />
<span style=”font-size: 12pt;”><strong><span style=”color: #000000;”>【漢字を覚える方法・ステップ3】は、</span><span class=”keiko_yellow” style=”color: #ff0000;”>セルフテストを数回行い、復習頻度上げることで覚えていきます。</span></strong></span>
いよいよ実践的な方法に入っていきます。
これまでにこの方法で、覚えることが苦手な子でも、100%成績をUPさせてきました。
効果がでるのに重要なのは、<span class=”keiko_yellow” style=”text-decoration: underline;”>正しいやり方で継続的に取り組めているかどうか</span>です。
昔は常識的だった、書いて書いて書きまくる方法よりも圧倒的に効率的で楽です。
ですが横着をしたり、継続できなかったりすれば当然、それに見合った結果しか出せません。
<h3>学級で漢字を覚える手順</h3>
具体的に、学校での学習から宿題までの流れを説明します。
<div class=”sng-box box6″>
①まず、新出漢字を人差し指で何度かなぞります。
・この時に、筆順を覚えてしまうようにと指示を出します
・筆順を声に出しながら、1,2,3,4となぞるか、情報量を減らすために声を出さなくてもよいです
②空中か机に人差し指で書いて、筆順を覚えているかチェックします。
・隣の子同士か、先生が前からチェックします
③漢字ドリルに実際に書き込みます。
↓ ここからが大事なところです。
④とりあえず<span class=”keiko_yellow”>2つ書き込んだら、書いた部分を消しゴムか下敷きなどで隠して、3つ目でセルフミニテスト</span>をします。
<img class=”wp-image-2621 aligncenter” src=”https://dylansensei.com/wp-content/uploads/2019/09/ドリル-1-1024×794.jpg” alt=”” width=”437″ height=”339″ />
⑤この時に覚えていなくても気にせず、正しい漢字を確認し直します。
(<strong><span style=”color: #ff0000;”>大事なのは、一回一回、気にしてへこまないこと</span></strong>です。)
⑥漢字ドリルはだいたい、5回くらい書きこめるので、<strong>2,3回セルフミニテストができます。</strong>
この<span class=”keiko_yellow”>セルフミニテストが脳へインパクトを与え、長期記憶への足掛かりになります</span>。
⑦【宿題】家に帰ってから、ノートに2,3回書いてから、セルフミニテストをします。
覚えてたら終わり。覚えていなかったら、また1,2回書いて、テストやって終わり。
</div>
多くの学級では漢字の宿題は、1ページや1行ずつ新出漢字を書きまくることが多いのではと思います。
<img class=”size-medium wp-image-2634 aligncenter” src=”https://dylansensei.com/wp-content/uploads/2019/09/ff1817fc516092aca4c2835a0d8c3041_s-300×225.jpg” alt=”” width=”300″ height=”225″ />
ディラン学級の宿題は、新出漢字1つにつき、熟語を3回~5回を書かせるしかさせていません。
そして、自分でミニテストをしてみて覚えていたら宿題終了です。
1日に新出漢字を4~5つくらい扱っていたので、宿題では20回くらいしか漢字を書きません。
量が少ないので、子どもは集中して取り組みます。
授業の残り5分間などのすき間時間にさせてあげると、すごい勢いで覚えようとします。
そして、<span class=”keiko_yellow”><strong><span style=”color: #ff0000;”>覚えることが目的ですから、多少字が乱雑でもO.Kにしています。(重要です。)</span></strong></span>
逆に、きれいな字を書けるようになるには、ある程度字数をこなさないといけません。
大事なのは、<strong><span style=”color: #ff0000; font-size: 14pt;”>目的にあった学習法をとっているか</span></strong>です。
<span class=”keiko_yellow”>宿題で20回くらいしか書いていないので、当然、頻度は低く、インパクトも薄いのですぐに忘れてしまいます。</span>
なので、<span style=”font-size: 14pt;”><strong>次の日にも同じ宿題を出します。</strong></span>
ただし量を減らして出します。マンネリ化を防ぐためです。
1,2回書くか、セルフテストをやってみて覚えていたら終了です。
なので、宿題としては、<span class=”keiko_yellow”>【当日の新出漢字4つ×5回 +前日の復習をサラッと】</span>
という感じになります。
だんだんと感覚を空けて、1週間、1か月と復習をすることで、記憶が強固なものになります。
このようにして、<strong><span style=”color: #ff0000;”>少しずつ記憶を上塗りして、長期記憶に変換していきます。</span></strong>
この方法を『上塗り記憶法』とよんでいます。
<h3>家でも継続的に行い、他の教科にも応用できる</h3>
<img class=”size-medium wp-image-2629 aligncenter” src=”https://dylansensei.com/wp-content/uploads/2019/09/2d9e17f6dea2bbb5e68ebfc5a5b5ea0d_s-2-300×225.jpg” alt=”” width=”300″ height=”225″ />
【上塗り暗記法】は歴史の単語や英単語など、さまざまな学習に応用可能です。
<div class=”sng-box box6″>
①何度か書く(乱雑でよい/少しの量だけ書く)
②セルフミニテスト(すぐに答えを確認/間違っても気にしない)
③時間をおいてミニテスト (少し時間をおく方が、記憶を呼び起こす力がつく)
④翌日、数日後に分けてミニテストで記憶の上塗り
(日が空きすぎると、覚え直すのに時間がかかる)
</div>
これで、テスト当日にも焦りません。
それまでに<span class=”keiko_yellow”>何度もテストのリハーサル</span>をしているからです。
テストは1回勝負という固定概念を捨て、何度も自分でテストを想定したセルフテストをすれば、テスト慣れします。
<span style=”font-size: 14pt;”><strong>暗記が苦手だという子も、正しい記憶法で学習すれば必ず成績は伸びます!!</strong></span>
記憶力が良いというのは、
<div class=”sng-box box8″>
<span style=”font-size: 14pt;”><strong>・長期記憶の倉庫に蓄積できるか</strong></span>
<span style=”font-size: 14pt;”><strong>・記憶を必要な時に引っ張り出してこれるか</strong></span>
</div>
ということです。
<h3>家でする際に気をつけていただきたいこと</h3>
<img class=”size-medium wp-image-2635 aligncenter” src=”https://dylansensei.com/wp-content/uploads/2019/09/1345c39171eec21d3d01980848ac042c_s-1-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ />
繰り返しになりますが、漢字のテストは正しいやり方でやれば、効率的かつ確実に成績を伸ばせることができます。
ですが逆に、子どもだけでの家庭学習には、個人の差が大きく出てしまうので、なかなか実力に結びつかないことも多くあります。
ぜひ、忙しい毎日かと思いますが、1日の内の10分でよいので、正しく学習できているかのチェックと、励ましのお声かけをしてもらえたら、子どもの成長は加速していくかと思います!
<h2 class=”hh hh16″>まとめ</h2>
<strong>・記憶のメカニズムを知り、忘れることが当たり前から始める</strong>
<strong>・記憶は薄くなるので、上塗りしていく</strong>
<strong>・ミニテストをくり返しすれば、テスト慣れして、本番でも良い点が取れる
</strong>
私は、漢字テストは成長を実感するための一つのツールというふうに捉えて学習指導をしてきました。
子どもに、できる・できないの優劣をつけるためのテストではなく、どのような努力をすれば、自分の力を伸ばすことができるようになるのか学んでもらう。
小さな成功体験を積み重ねるためのものだと考えています。<span style=”letter-spacing: 0.8px;”> </span>
自分はやったらできるんだという自信をつけさせるそのためには、テストは良い点を取れる方がよいにきまっています。
これまで辛い思いをしてきた子の成績が上がるよう、少しでもお役に立てたら幸いです。
ぜひ、この記事も参考にしながら、本来のお子さんの力を伸ばしてあげてくださいね!
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!