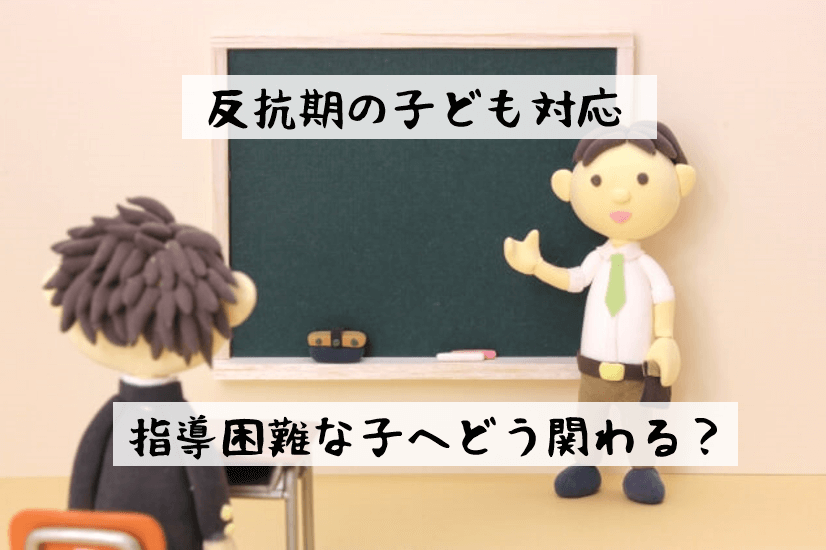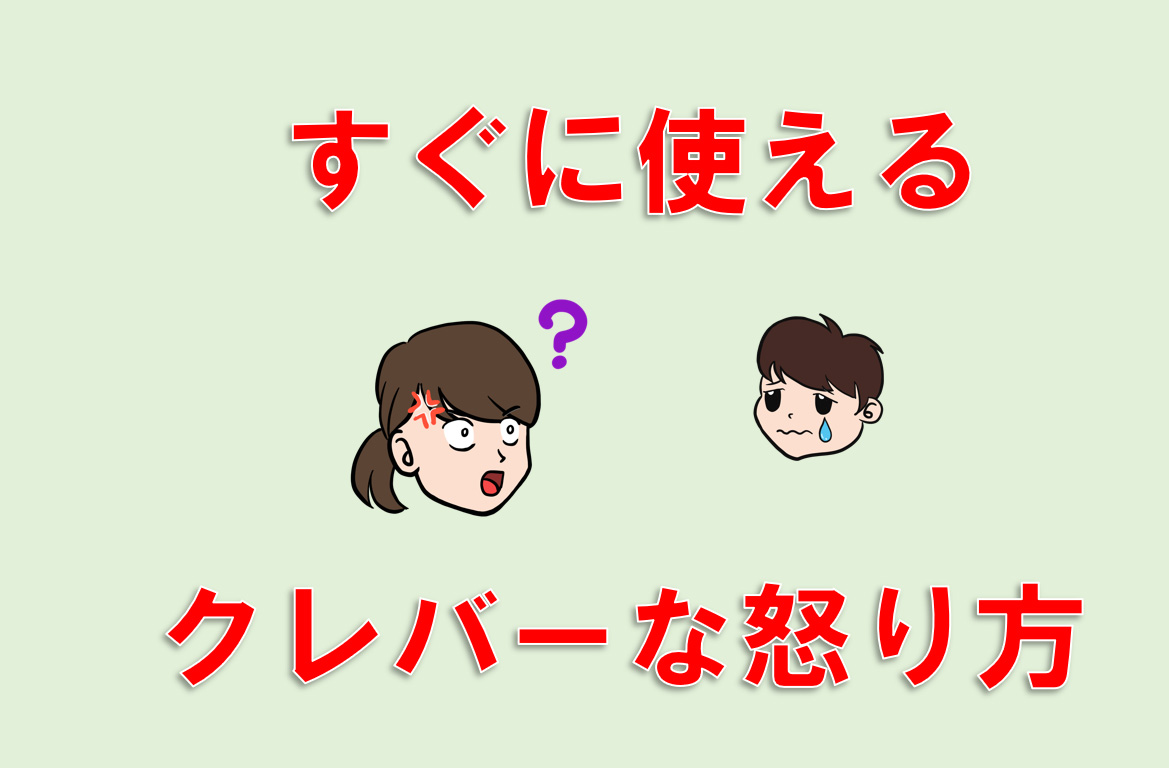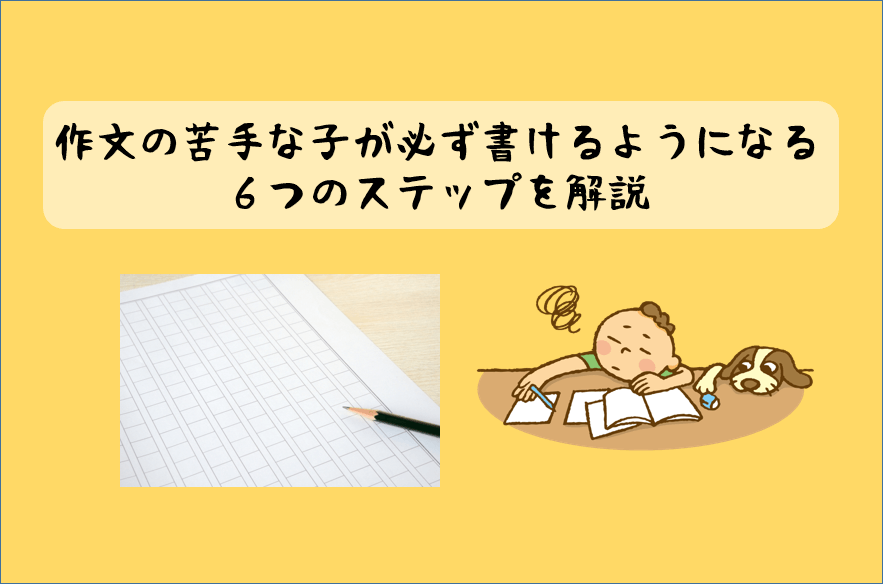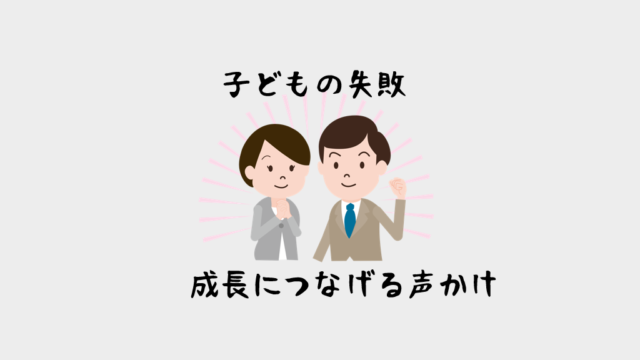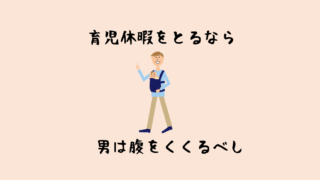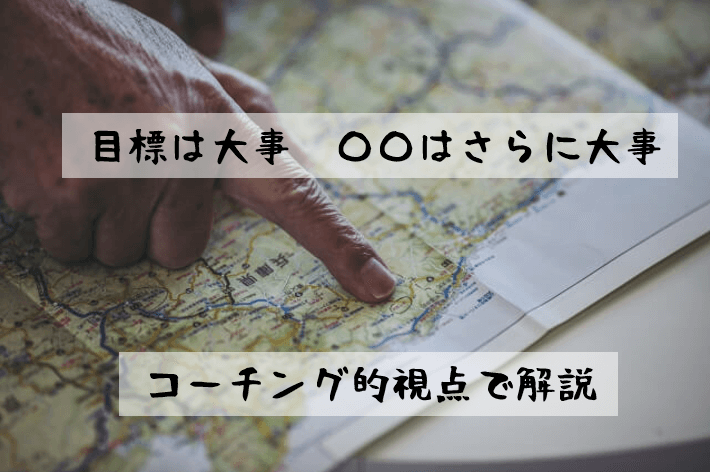子育てをするうえで、わが子の問題行動や、反抗的態度は深刻な悩みの種ですよね。
私もこれまでに、学校現場で頻繁にトラブルを起こす児童との関わりも多くありました。
これまでの経験の中から、指導困難な児童との関わりの中で見つけた、子育て、教育で大切にしたいことを紹介したいと思います。
とにかく問題ばかり起こす男子児童
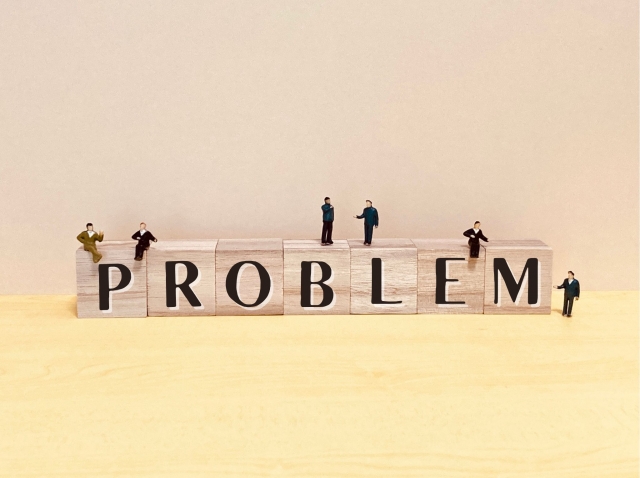
ある年に担任として関わった男子児童ですが、とにかくトラブルを毎日起こす子でした。
あまりにも周りの子とのトラブルが続くので、もういい加減にしてほしいと疲弊してしまっていた時期もありました。
前年度からの引継ぎもあったので、ある程度の予想はできていましたが、学年が1つ上がることは体も心もパワーアップするわけで、想像をはるかに超えて苦戦していました。
その子がたまたま休む日は、クラスの雰囲気も穏やかで、普段どれだけその子にパワーを費やしてきたかを感じます。
教師も人間です。
その当時は正直、いないことにホッとしてしまう自分と、いやいや、彼だって大事なクラスの一員と思い直す自分との葛藤に揺れていました。

今振り返れば、その子と出会えたことで、私のコミュニケーション能力も、指導力も数段向上したと思えます。
私にとっては必要な出会いでした。
とことん悩み、いろいろな方法での関わりを試すなかで、その子にはこれだ!という確かな手ごたえを感じる関わり方がありました。

全てのスタートはラポール形成から

子どもとの関係性はダイレクトに指導に影響を与えます。
子どもは正直ですから、信頼していない、好きでもない大人の言うことは聞いてくれません。
表向き、聞いているように見えても、それは”怖いから” や ”うるさいしめんどくさい”から聞いているふりをしているだけで、心には届いていません。
ラポールとは、信頼関係。
心と心に橋が架かっていなければ、なかなか心の内は見せてくれないし、こちらの言葉も受け取ってくれません。
知ってはいるものの、ラポールを築くまでにうまくいかないこともあります。

先ほどの男子児童のケースでは、出会いの当初はとにかく対話をして、相手の思いを引き出すことに力を注ぎました。
その頃はコーチングも学んでいたので、引き出すことは得意だと思っていました。(勘違い?思い上がりだったのですが・・)
トラブルが起きた時、はじめの頃は自分の思いを話してくれて、今後の適切な行動も考えてくれていましたが、回数を重ねるごとに、私から逃げ出すようになりました。
私は、話せばわかる。話さなければ何も変わらないと思い、だんだんとイライラが募っていきました。
時には、大きな声で怒鳴って指導するようにもなりました。

違うような気もするけど、いけないことをしているんだし、厳しく叱らないといけない場面だと、心を鬼にしてその子と関わるようになりました。
そうするとどうなっていったか。
私に対しても反抗的な態度でかかってくるようになりました。

そしてそれをまた、力で抑えつける。どんどん悪循環の深みにはまっていきました。
その頃は、完全にラポールは切れていました。私が引きちぎってしまったようなものです。
うまく改善されないことで疲弊もしていたし、焦りもあったため、とにかく変化を求めていました。
もう、この子とはうまくやっていけないと思っていましたし、関係の修復も無理だと半ば諦めていました。
早くその年度が終わってほしいとも思うようになっていました。

相手を変えるのではなく理解すること

とことんうまくいかなかったその男子児童との関係が好転し始めたのは、半年を過ぎた頃でした。
それまで様々な心理学を学び、相手の価値観を変えて悩みを解消するワークなどを身に付けていたので、その子を良くするためにいろいろな方法を試してきました。
ですが、そこがそもそもの誤りだったことに気付いたのです。
あるコーチングのテキストを久しぶりに読み返していると、「相手を変えるのではなく、理解しましょう」という言葉が目に入りました。
気づけば、自分は真逆のことをしていたのです。

その子を悪だと決めつけて、自分の常識や正しいと思う価値観でその子を裁いていました。
相手の思いを引き出していると思い込んでいるが、やっていることは自分の価値観の世界に知らぬ間に引きずりこもうとしていたのです。
そりゃ逃げるよなと後から思いました。
それに気づいてからは、とにかくまず、これまで以上にその子の話をしっかり聴くことに専念しました。

どんないたずらやトラブルであっても、こちらの評価や分析を挟まずにとにかく聴き、承認しました。
「そっか、それでカッとなったんやね」「それは確かに嫌になるよね」「そう思って手がでたんやね」
そして、聴ききった後、
「また同じようなことなったらA君がまた1人悪者みたいになってしまうやん?
腹立った理由も先生も分かるから、みんなにも腹が立った事情を伝えられたら問題起きないかなと思うけどどう思う?」
のような、「僕はこう思うんだけど、どうかな?」と提案するかたちで関わるようにしました。
すると徐々に、トラブルを起こした後でも自分の良くなかった行動を認めることができるようになり、素直に話を聴いてくれるようになってきました。

すぐには状況は変わらない。けどそれでいい
ここで誤解を与えてはいけないと思うので書いておきますが、
徐々に話を聴いてくれるようになるまでには、前進もすれば後退も繰り返しました。
相変わらず、毎日のようにトラブルは起こりました。
”このスキルを使えば、子どもはすぐに良くなる”
そんな魔法は存在しないと、私は思っています。
子育て、教育は1歩進んで3歩下がる日もあれば、1歩も進む気配もない時もあります。
でも、それでもいいと思っています。

親、指導者は、良くならない現状が続くと焦りだすのですが、そもそも、その焦りやイライラは誰のためにあるものなのかをしっかり見極める必要があります。
この子に対して、ほんとうに些細な頑張りでもこまめに取り上げて、承認を繰り返し行っていきました。
あらゆる場面で、感謝の気持ちを言葉で伝え、けがをしたときは心から心配している姿で接しました。
そうやって、引きちぎってしまったラポールを修復するために本気で関わりました。
これまで、何度も何度も、大人からも周りの友達からも怒られ、非難され続けていたために、もうこれ以上自分が傷つかないために、反抗的な態度を取らざるを得なくなってしまっていたのだと思います。

だから、変わることは怖いし、時間がかかる。
それに気づいたとき、無条件でその子が愛おしく思えました。
時間がかかってもいい。
どんなあなたであっても、僕はあなたを応援する。
その思いを捨てなければ、いつか思いは届きます。
これらが、失敗だらけの関わりを通して見つけた、子どもとの関わりで大切にしたいことです。
まとめ
子どもはすぐには変わりません。
そもそも、大人の価値観に子どもを合わせようとする時点で、子どもへのリスペクトが失われています。
不適切な行動をとる子どもにも、何かしらの思いや目的があります。
答えをすでに持っている大人の目線から、それは間違っていると決めつけてかかると、そこに摩擦が生まれます。
こちらの思いや話を届けたいのであれば、まずは落ち着いて、子どもの話を無条件で受け取ることが大切だと思います。

とはいえ、これがなかなかできないんですけどね。
お互いに”思い”がありますから。
できるようになれば、子どもとの関係は必ず変わります。
なぜなら、その行動ができるようになっているとき、それは、大人の在り方が変わっているからです。
そうなれば、子どもの大人を見る目も変わってくるかと思います。
あなたの心が晴れますように!
最後までお読みいただきありがとうございました。